視機能検査は、検眼や眼鏡フィッティングにおける重要な専門スキルの一つであり、中上級の検眼士や眼科医が備えていなければならない専門スキルの一つでもあります。
視機能検査は消費者の視力の健康状態を診断する上で非常に重要であるため、視機能検査の方法は充実・発展してきました。ここでは、視機能検査のいくつかの方法をまとめ、参考としてご紹介します。
NO.3 調節柔軟性テスト
球面鏡反転法
球面ミラーフリッピングラケットは、フリッピングラケットに取り付けられた±2.00の球面ミラーのペアで構成されています。異なる度数の2つのレンズによって引き起こされる調節刺激は、0.50Dと4.50Dの間で切り替わります。
操作手順:
① 検査眼の屈折異常の矯正
② 検査する目の最も近くを見る視力の上のラインにある視力マーク、または20/30の視力マークカードを選択します。
③ 検査を受ける人は近視マークカードを持ち、目の前40cmのところに置きます。
④ 左目を覆い、まず+2.00Dのフリッピングラケットを右目の前に置き、テスト開始点として視覚的なマークが鮮明になるのを待ってから、-2.00Dのフリッピングラケットを目の前に置き、時間を計測し始めます。
視標が明瞭になった後、直ちに+2.00Dのレンズを目の前に置き、視標が明瞭になるまで待ちます。この時点で最初の切り替えが完了します。上記の切り替えを繰り返し、1分間の切り替え回数を数えます。
⑤ 同様の方法で左眼の調節柔軟性と両眼の調節柔軟性を測定する。
⑥ 調節柔軟性検査の結果を記録します。正常値:5~15セント/分(両眼)。

NO.4 収束近傍点チェック
① 被験者は適切な距離補正眼鏡をかけ、被験者のトライアルフレームまたは眼鏡フレームの横に測定定規を置き、測定定規の0の位置がレンズ面になるようにします。
②被験者に両目で単列の照準マークを見てもらい、単列の照準マークを40cmから両目まで一定の速度で移動させる。
③被験者が単列視標が複視していると言うまで、そのときの距離を測定定規で読み取ります。
④ 被験者の遠距離瞳孔間距離を測定する。
⑤ 被験者の単列視標が複視に見える点から両眼回転点(角膜後13mm)までの距離(輻輳近点距離)を記録する。
⑥被験者の両眼瞳孔間距離と検出された輻輳近点距離値に基づいて、被験者の輻輳振幅(正常値:2.5~7.5cm)を計算します。
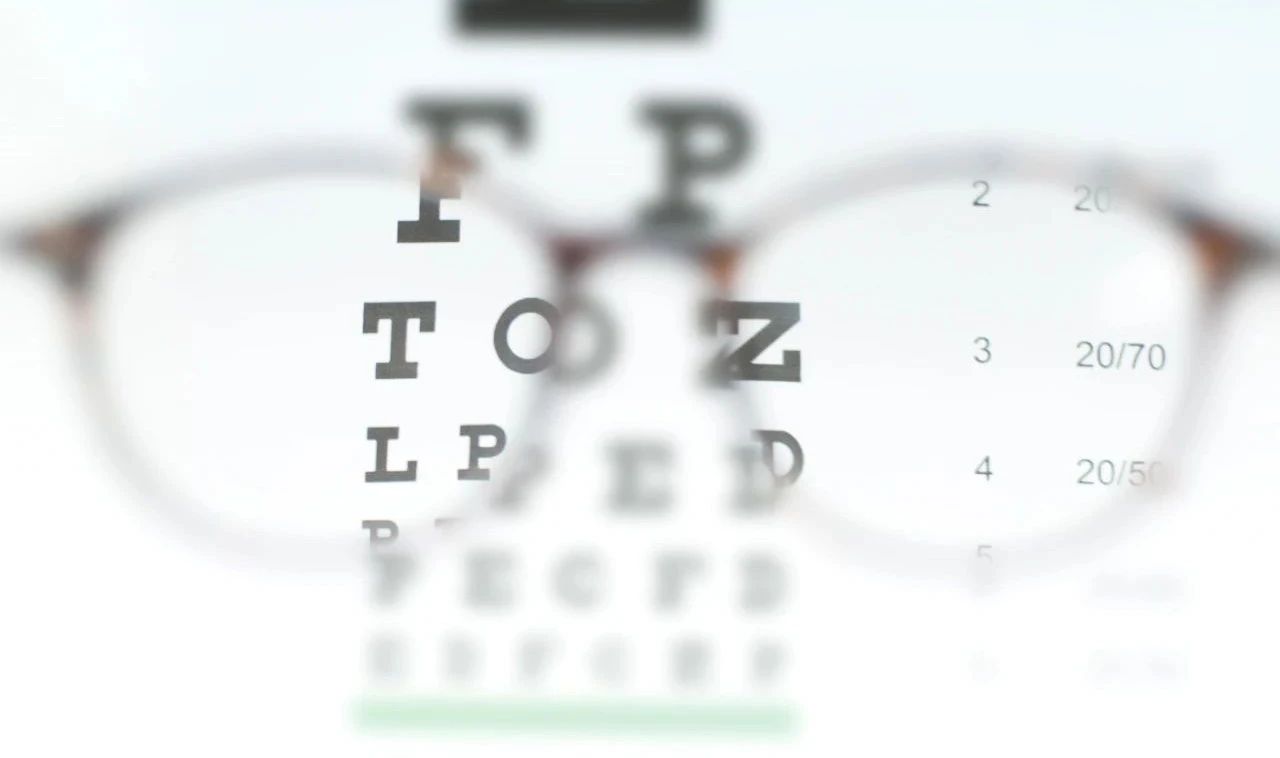
NO.5 収束柔軟性テスト
操作手順:
① 屈折異常を完全に矯正する
② 底面を内側にしたプリズム3個と、底面を外側にしたプリズム12個をフリップカメラに挿入し、フリップカメラの瞳孔間距離を調整します。
③被験者に40cmの単列照準を見つめさせ、3つのプリズムを底面を内側にして被験者の目の前に置き、照準が1列になるまで置きます。
④ 12個のプリズムを底部を外側に向けて入れ替え、被験者の目の前に置き、時間を計測します。
⑤ 被験者に40cm単列の照準マークを両眼で見つめさせ、像の融合を試みる。双眼の照準マークが融合したら、再び3つのプリズムを内側に向けて切り替え、双眼の照準マークが融合するまで繰り返す。これを切り替えサイクルとする。
⑥ 検査対象の目が1分間に何回スイッチングサイクルを完了するかを測定します。
⑦ 人口の正常値、正常な両眼輻輳柔軟性は1分間に12~18回です。
投稿日時: 2024年6月21日

