視機能分析の3大ルールは、主に①1:1ルール ②Pルール ③Sルール の3つを指します。今日は3つ目の【Sルール】について学びます。SルールのSは(刺激-反応)の略で、主に両眼視における調節と輻輳の関係を分析するために用いられます。まずは、調節と輻輳の基本的な概念を理解する必要があります。調節とは、近くのものをはっきり見るために目の屈折力を変えるプロセスであり、輻輳とは両眼が同じ対象に焦点を合わせることができるように両眼の視軸を変えることです。Sルールを用いて分析する際には、調節反応(BCCやMEMなどの方法)と輻輳能力(斜位の遠近距離と融合距離を含む)を測定する必要があります。
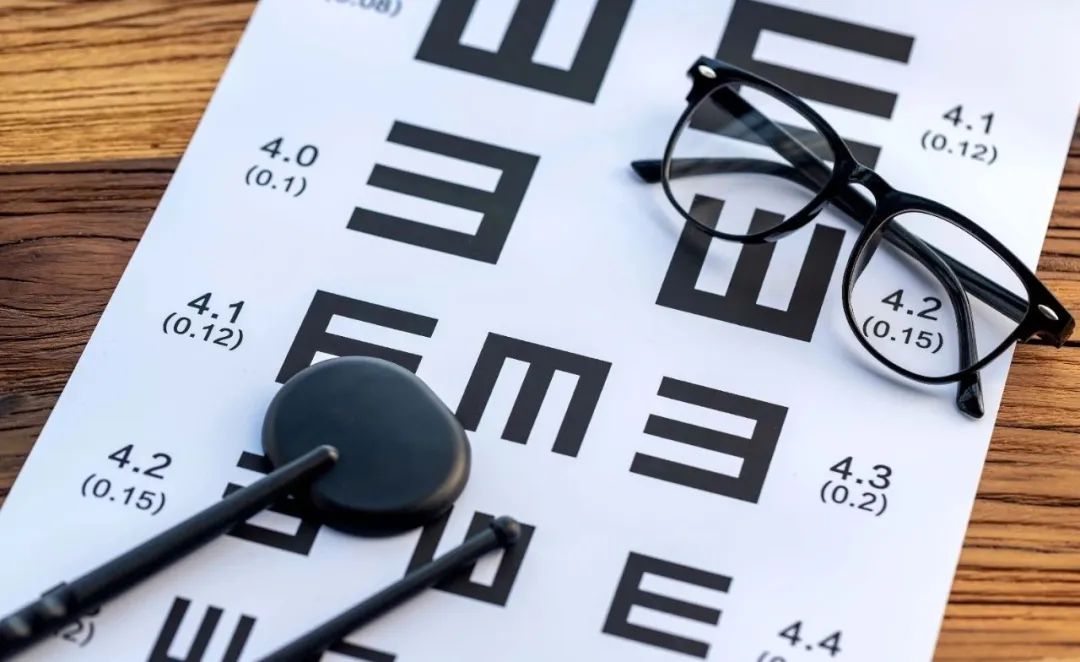
家族は裕福(正常適応)ですが、それでも買い物をする際には倹約し(適応ラグ)、できるだけ出費を抑えなければなりません(適応をできるだけ使わずに済む)。適応能力は加齢とともに低下します。適応能力が低下するのは、お金を使いたくない(適応ラグ)のではなく、使えるお金がない(適応がない)状態です。したがって、高齢患者の適応反応を検査することは意味がありません。
投稿日時: 2025年3月7日

