誤解 1: 眼鏡をかけると目が変形する。
目の変形は近視による眼軸の延長の結果であり、眼鏡のせいではありません。
誤解 2: 真性近視と偽性近視に違いはありません。
いわゆる「仮性近視」は、過度の眼精疲労によって引き起こされる視力低下であり、一時的な場合もあります。散瞳検眼後、軽度の遠視、または近視がないことが示され、これは完全に正常な屈折状態です。この場合、眼鏡は必要ありません。多くの親は、散瞳検眼を行わずに眼鏡店で子供に眼鏡を合わせるのを面倒に感じており、散瞳検眼は最終的に仮性近視を真の近視に変えてしまいます。
誤解 3: 眼鏡をかけると近視が悪化する。
多くの親は、眼鏡をかけると近視がどんどん深くなると考えています。実際には、遺伝的要因に加えて、思春期に近視が深くなる主な原因は、近距離を過度に使うことや、科学的な目の習慣の欠如です。適切な眼鏡をかけることで、近視の深まりを効果的に防ぐことができます。
誤解4: メガネを合わせるときは、度数を下げる必要があります。
メガネの度数は正確でなければならず、「過剰矯正」や「余裕あり」は禁物です。「過剰矯正」はメガネをかけた後、お子様がめまいを感じる原因となり、「余裕あり」は近視を悪化させる可能性があります。メガネを合わせる際は、お子様がメガネをかけた後、長時間、はっきりと、快適に物が見えるようにする必要があります。
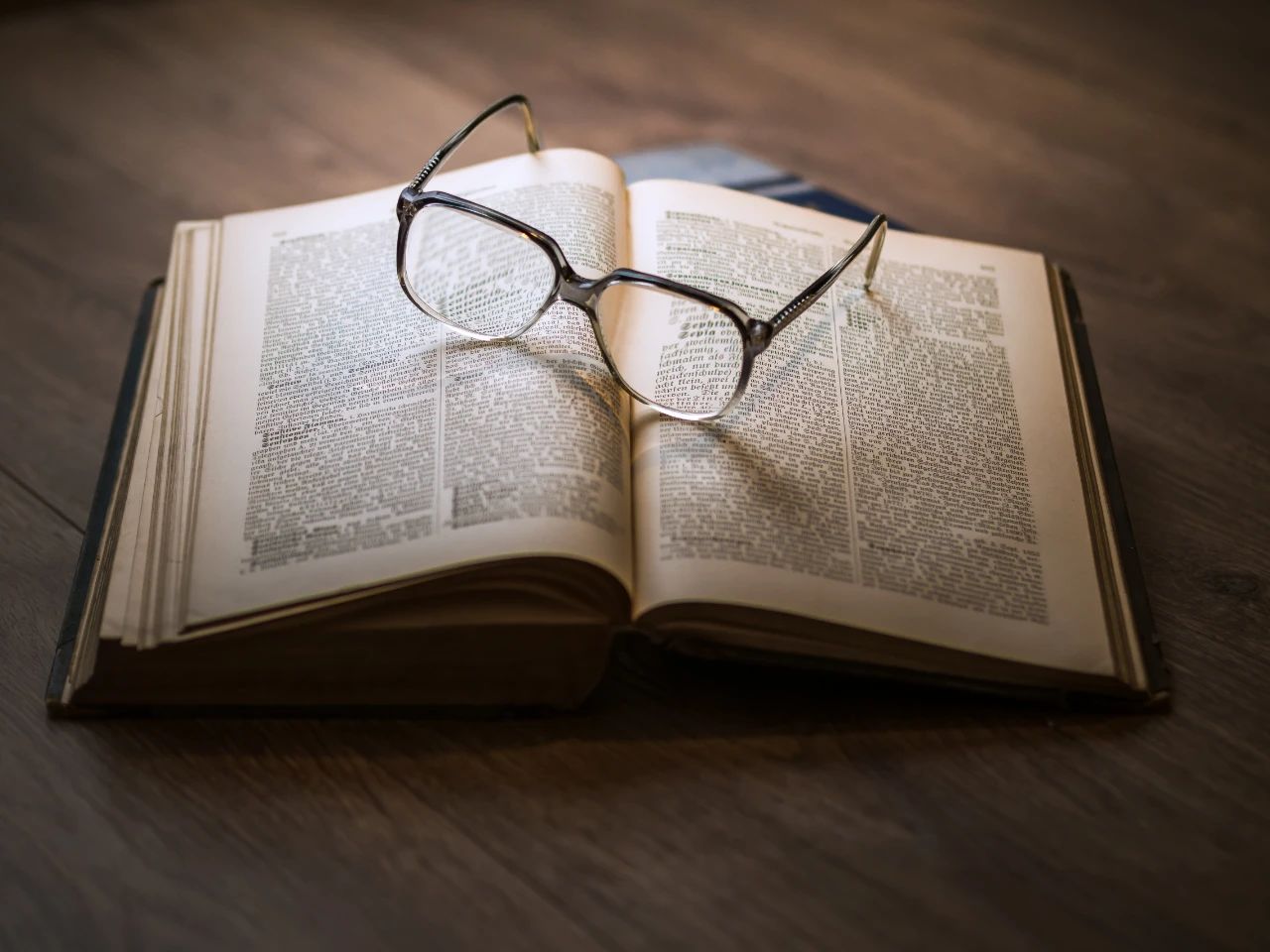
子どもがすでに近視の場合はどうすればいいでしょうか?
まず、真性近視か偽性近視かを判断します。かかりつけの病院の眼科を受診し、医師による散瞳後の結果を確認するのが最善です。散瞳後の屈折力が正常であれば偽性近視、近視であれば真性近視です。
擬似近視
仮性近視は真の近視ではなく、過調節によって引き起こされる近視です。長時間、近くを見続けると調節痙攣(遠くのものがはっきり見えなくなる近視現象)を引き起こします。お子様が「仮性近視」の場合は、近くを見る回数を減らしたり、毛様体筋麻痺薬を使用したりすることで、お子様の目を完全にリラックスさせ、ゆっくりと回復させることができます。
真の近視
一方で、医師や検眼医のアドバイスに従い、子供は近視を矯正するために適切な時期に眼鏡をかけるべきです。同時に、日中の屋外活動を強化し、近視の進行を抑えるために、目を近づけたり電子機器の使用を減らしたりすることにも注意を払う必要があります。同時に、3~6ヶ月ごとに病院を受診し、視力、眼軸、屈折の状態を検査し、子供の近視の進行状況を動的に把握し、適切な介入と抑制措置を講じる必要があります。
投稿日時: 2025年7月11日

